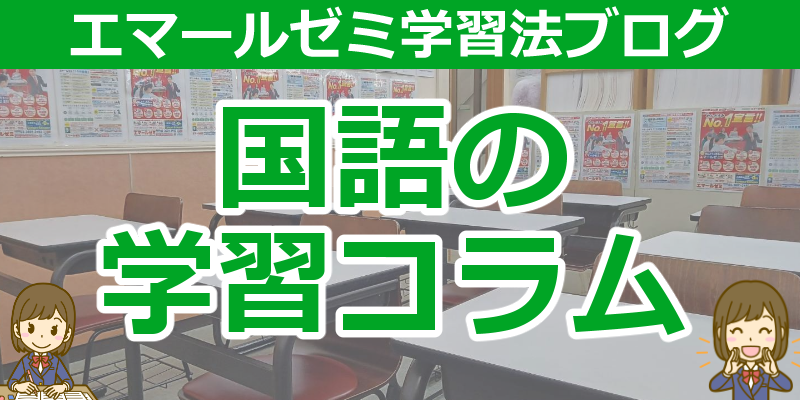
国語という教科は、勉強という場でだけのものではなく「日々学習」であると思われます。
人の話を正確に聞き取り、かつ自分の言いたいことを的確に人に伝えられる力、あるいは他人の「心の風景」が推察でき他人と不必要にぶつからない能力も国語の力と関係していると思われるからです。
さて、ここではまず国語を入試の観点から説明的文章と文学的文章に分けて、説明的文章における論説文(多くの生徒が苦手な分野です)から書いていきます。
入試科目としての「国語」
最初に感じることは、小学生・中学生・高校生にとっては勉強という場以外では入試でテーマになりうる「科学技術」「異文化を含めた文化」「言語」「哲学」などを主体的に学びしっかり考えることが少ないようであるということです。
(少なくとも学校では教科書のテーマには触れているはずではあります)
例えば高校入試問題で、時には中学入試ですら大人が読んでも決して易しくはない論説文が出てきますから、主体的に意識し知識を得ると同時に様々なテーマにについてしっかり考えてみることは忙しい学生にとってほとんどないことが現状かもしれません。
であれば、学校や塾で国語の教科としてきちんと向き合うことが重要になります。
義務教育ではない高校で学ぶ入口となる入試問題における論説文では、先ほど話した事柄について全く考えたことのない生徒らにとっては読みづらいことは当然でしょう。
中には日ごろから日々社会で取り上げられる出来事について家族で話し合うことが生活の一部になっている家庭もあるようです。
このような環境に育ったお子さんはやはり読解力が強いようです。
ところで、国語における論理は算数・数学の論理とは少し違って白と黒ではなく灰色な部分も多いものですが、読み方は論理的な演習が必要になってきます。
よくあるのが個々の文は読めてはいても全体像がわからない、つまり要旨がつかめていないケースです。
そのためには一つ一つの文の意味だけではなく筆者の言いたいことを読み取る、言うなれば「つなげて読む(文章全体のメッセージを頭の中でつなげるということ)」ということです。
これは訓練しなければなかなかできるものでもありません。
正しく読む演習ということです。
この場合は精読(=細かいところまで注意して読むこと)であり学校や塾で読む方法です。
読解力が伸びる条件としては精読と多読(本を多く読むこと)と言われますが、この演習に加えて多読つまり自主的に本を読む習慣があれば「鬼に金棒」です。
〔中編はこちら〕
