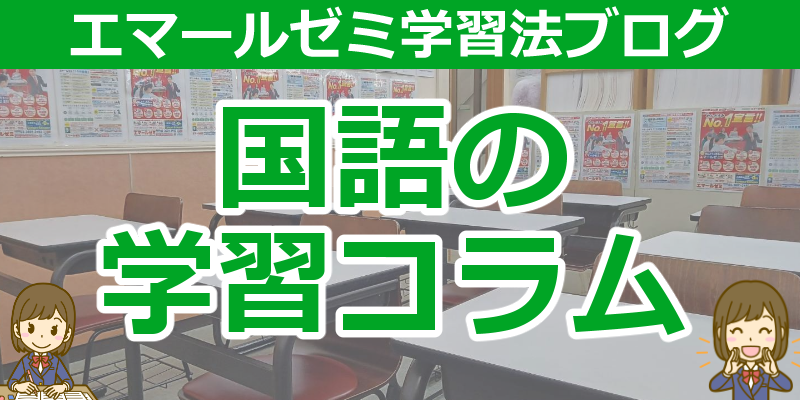
〔前編はこちら〕
今回は文学的文章について書いていきます。
小説・随筆は一言で言えば、他人の「心の風景」が読めるようになることが大切なのですが、他人は自分とは異なり十人十色様々な性格あるいは価値観を持った人がいることをまずは知ることでしょう。
国語は日々学習であると前編で書きましたが、小さいうちから多くの兄妹と関わる、あるいはサッカー・野球のような団体スポーツに精を出していれば協調性が培われているはずですし、その意味で国語的な力がよりあることが多いかもしれません。
ただし入試で出てくる問題では文字から登場人物の「気持ち」あるいは「気持ちをの変化」を読み取らなければならないので、自分とは異なるいろいろな人とうまく向き合うことが出来るとしても文章から他人の心の風景が読めるかどうかについては別問題という面があります。
「文字だけ読む」ではなく「心を読む」
子供たちの中には、物語を読んで特に何にも感じていないと思われる生徒がいるのですが、文字は読めてはいても「心で読めていない」、つまり言葉から情景を読み取り、登場人物の立場になって読んでいない読み方をしているのでしょう。
(文字面しか読んでいない、あるいは想像力を巡らせられず感情移入が出来ていないということです)
逆に国語が得意な生徒は物語を読みながら心では微笑んだり、怒ったりあるいは泣いたりもするはずです。
授業中に涙ぐんでいるというより泣いている生徒がいたことがあり、後日聞いたところ話に感動したとのことでした。
授業中という状況にもかかわらず涙がこぼれてしまうとは、よほど内容に感情移入しやすい一途な性格でもあったのでしょう。
いずれにしても、本の楽しみ方を知った生徒は強いです。
小学生であれば絵本でもいいので本から感動する機会を作ってあげたいものです。
