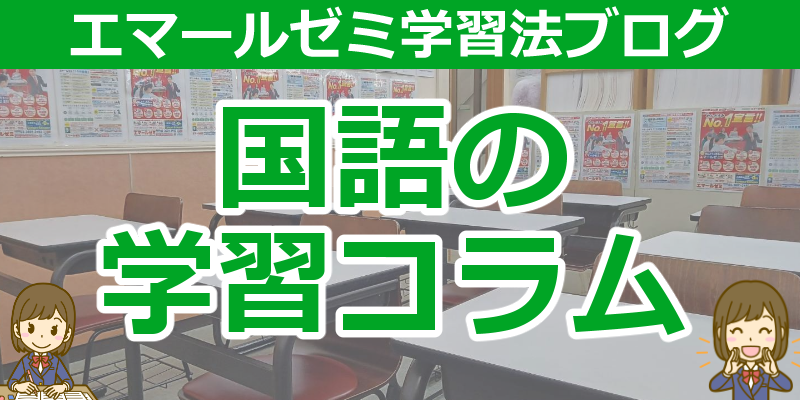
〔中編はこちら〕
さて、最終回は入試から離れて日本語というものについて考えてみたいと思います。
日本語というよりも言語というべきですが、言語と思考の関係は非常に密接です。
人間は言葉を持つからこそ、動物と違って過去のことや未来のことまで考えることが出来るのであり、おそらくは言葉がなければ深い思考はほぼ出来ないでしょう。
ですから、語彙が増えればその分だけ人の感覚が豊かになることを意味するものです。
さらには語彙を増やすことによって基本的には考えるためのツール(武器)が増えるものなのです。その意味で国語は知的活動における基礎であり、他教科にも影響を及ぼす割合が大きい教科と言えます。
日本語について
日本語というものは感覚を表現する言葉が例えば英語と比べると多いですし、それを駆使して日々を生きていくわけですから、大げさに言えば国民性につながるのではないでしょういか(英語は否定語も主語の後にすぐ来ますし、文章も「結論ファースト」です)。
良し悪しの問題ではなく、言葉自体にそのような傾向があります。
そのために日本人が持っている傾向が強いと思われる「礼儀を守り、謙虚で相手を気遣う」傾向が心の中に刻まれてきていると思われます。
また、日本の古典を含めた文学は自主的に本を買って読まないにしても皆学校で学ぶものです。
もちろんその影響の程度は人によって異なるでしょうが、少なくない日本人は日本の文学作品を読んだり、日本のドラマを見たりしているうちに知らず知らずのうちに「日本的」な面が身に付いてきているとのでしょう。
例えばノーベル文学賞を授与された川端康成は「日本の美しさと哀しさ」を書くと述べましたが、「伊豆の踊子」にも「雪国」にもその繊細な日本独特の感性である豊かな情緒が散りばめられており、平安文学の美的理念である「もののあはれ」ともつながるものです。
世界一短い詩歌である俳句が生まれたのも日本語ならではのものだと思われます。
